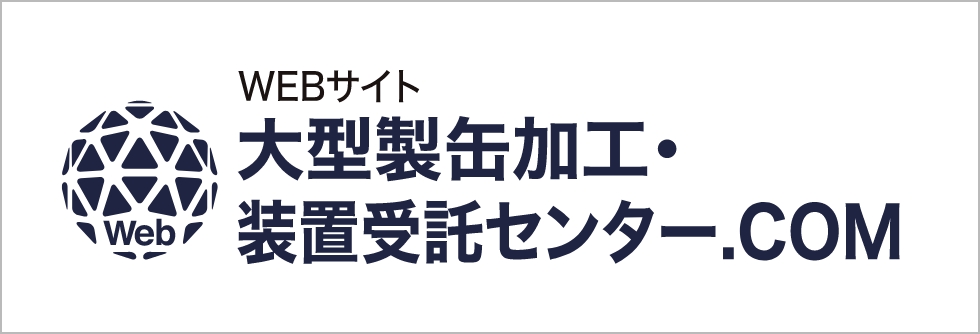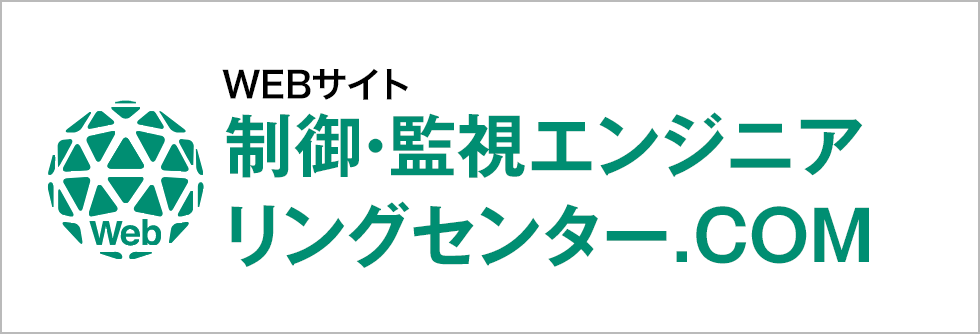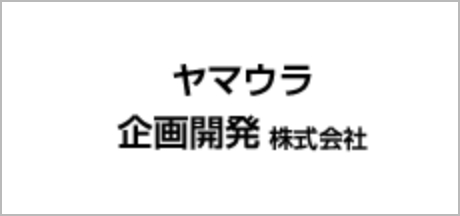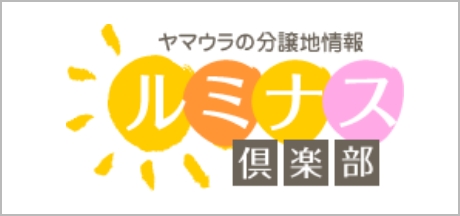よくある質問 / FAQ
インフラ技術ナビへ よくある質問
- 小水力発電を設置するときに関連する条例、法規はどんなものがありますか?
-
小水力発電の利用にあたっては、工作物の規模や出力の大小に係わらず河川法に定められた許可が必要になる場合があります。
参考例としてはFIT法、電気事業法、農地法、森林法、都市計画法、道路法、砂防法、自然公園法、河川法、騒音規制法、建築基準法、消防法等の多くの認可を得る必要がございます。このような申請業務をお客様のみ実施していただくのは、非常に骨の折れる内容でございます。そこでインフラ技術ナビを運営する株式会社ヤマウラが申請業務を含めた事業性評価から詳細計画までの一貫代行させていただくことでお客様の工数の削減を可能にしています。小水力発電を検討されている方は、検討段階からまずはご相談ください。
条例・法規の詳細は下記のサイトをご覧ください。(参考:自然エネルギー庁 事業計画策定ガイドライン(中小水力発電)https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/saisei_kano/pdf/010_s02_03.pdf)
小水力発電
関連する質問
- 幅:3.6m、高さ:6.2mの背面降下前面掻揚式除塵機のチェーンローラーの摩耗が激しく、困っています。原因について教えてください。使用年数は5年、使用頻度は年間500時間ほどです。やや濁りのある水質環境で、チェーンメーカーとスプロケットメーカーは異なるものを使用しています。
-
チェーンローラーの摩耗が著しくお困りとの事ですが、製作メーカー様の設計思想もございますので、考えられる一般的な原因をご回答致します。
①ローラーの摩滅が著しい為、レール上を転動するような構造になっていないように思われます。
②ローラーの材質は?レール材質に比べ摩滅しやすい材質になっているように思われます。
③いづれもレーキ下側のローラーである為、掻き揚げ荷重が設計値限界に近く、ローラーへ過剰な負荷が加わっているように思われます。以上のような原因が考えられます。
使用年数5年程度としては摩耗が早いように思われます。
一度、納入メーカー様に見解を伺ってみてはいかがでしょうか。
- 工場の排水溝の除塵を検討しています。図面と写真をお送りすればよいでしょうか?
-
除塵機のお見積りをする際は、その他にも情報をご共有いただく必要があります。例として、土木構造図と設計諸元をいただければ、スムーズに概算お見積りを作成することができます。
- 通常の自動水門では開閉に時間が2分ほどかかるようですが、もっと早く水門を閉じたいです。どれくらいのスピードで水門を閉じることができますか?
-
電動水門については、ある程度の時間がかかってしまいます。そのため、工場内の緊急時の遮断用途での水門利用をご検討されている場合は、どのような環境と条件なのか、水門の設置箇所等、水門の設計等、製作の前段階からご提案させていただきます。
- 全部で5工場ある組立工場にて、環境事故防止のために、すべての排水口に自動水門(手動水門の自動開閉追加)の設置を計画していますが、ご相談に乗っていただけますでしょうか。
-
はい、対応可能です。工場内の土木構造図や水門の設置方法についてレクチャーをさせていただきます。
- 用水路で、水中ポンプの前に「無電源バースクリーン式農業用水路用除塵機」の設置を検討しております。お見積りいただくのに必要となる条件等を教えていただければと思います。水路幅は2.4m、水路高は4mに設置予定です。
-
正確にお伺いしなければご回答が困難となりますが、該当の水路サイズでは無電源除塵機での製作は困難だと想定されます。
代わりに当社では、バースクリーン式タイプでのご提案も可能です。2連式にすることで幅を満たすこともできます。
まずは設計諸元についてご教示いただけましたら、その諸元にあったご提案をさせていただきます。
- 他社メーカーが製作された除塵機の修理は可能でしょうか?
-
誠に恐れ入りますが、他社で製作された除塵機の修理についても多くご相談を受けておりますが、現状はお受けしておりません。除塵機の更新の際には、ぜひ当社までご相談いただければ、より効率が良い除塵機のご提案をいたします。
- 御社で動力源を水車とした除塵機を製作されていますでしょうか。電気を必要としない除塵機があれば、ご紹介頂けないでしょうか。
-
カタログ及び設置条件をご連絡させていただきます。
- 水車を動力とした、水路用無電力除塵機を検討しています。設置条件にポイントはありますか?
-
水車を動力とした除塵機は、ちょっとした設置条件がございます。
①動力源である水車はスクリーンの下流に設置されるため、
水路幅:1m以上 水路長:3m以上の直線水路が必要です。②水車は整流の状態で、0.6m/sの流速が必要となります。
③水車を回転させる為、最低でも30cm以上の水深が必要となります。
- 福岡県で雨水排水機場の自動除塵機を計画しておりますが、九州でも対応可能でしょうか?
-
設計~製作は可能と思われますが、営業エリアを超えてしまう為、現地にて据付工事や保守メンテナンスを実施いただける業者様を開拓する必要があります。
- サ-ジタンク(貯槽)除塵機の更新に伴う見積をお願いしたい。
-
御見積可能と思われますが、特殊な設置条件や仕様がございましたらご教示ください。
 関連リンク
関連リンク
「高品質」「顧客満足度の向上」をモットーとして、さまざまなサービスを展開しています。